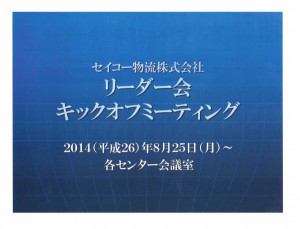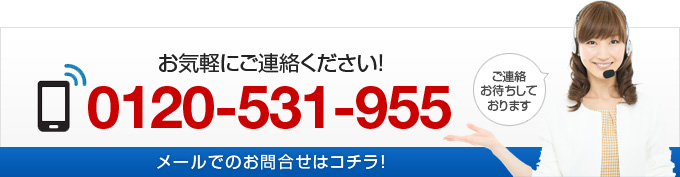2014еєігВВгБВгБ£гБ®гБДгБЖйЦУгБЂжЬАзµВжЬИгБ®гБ™гВКжЕМгБЧгБПгБ™гБ£гБ¶гБЊгБДгВКгБЊгБЧгБЯгАВгБХгБ¶гАБеЕИгБ†гБ£гБ¶и°МгВПгВМгБЯгГ™гГЉгГАгГЉдЉЪгБЃгБФ冱еСКгБІгБЩгАВ
дїКеЫЮгБЃгГЖгГЉгГЮгБѓгГЮгГКгГЉгБ®гВ®гГБгВ±гГГгГИгБІгБЩгАВе∞Пе£≤ж•≠гБЃзЙ©жµБгБІгВВзЙєгБЂгВ≥гГ≥гГУгГЛгВ®гГ≥гВєйЕНйАБгБѓгБКеЃҐжІШгБ®еРМгБШйІРиїКе†ігБЂгГИгГ©гГГгВѓгВТж≠ҐгВБгБКеЃҐжІШгБ®еРМгБШеЕ•гВКеП£гБІеЇЧеЖЕгБЂеЕ•гВКгБЊгБЩгАВеЇЧеУ°гБЃжЦєгБ®еРМжІШгБЂгБКеЃҐжІШгБЄгБЃжМ®жЛґгГїж∞ЧйЕНгВКгВТгБЧгБ™гБМгВЙгБЃзіНеУБгВТи°МгБДгБЊгБЩгАВ
гВ®гГБгВ±гГГгГИгБ®гБѓгАБеАЛдЇЇгБЃиЇЂгБ™гВКгВДжМѓгВЛиИЮгБДгАБи°МеЛХгВТйАЪгБЧгБ¶дЇЇгБЂињЈжГСгАБдЄНењЂгБ™жАЭгБДгВТгБХгБЫгБ™гБДгБУгБ®гАВвАїгВ®гГБгВ±гГГгГИгБЃи™ЮжЇРгБѓгГХгГ©гГ≥гВєи™ЮгБІи®АгБЖзЂЛгБ¶жЬ≠пљ£гБІгАБгБЭгБЃжШФгГЩгГЂгВµгВ§гГ¶еЃЃжЃњгВТдЄАиИђж∞Си°ЖгБЂйЦЛжФЊгБЧгБЯжЩВгБЂж∞Си°ЖгБМзЯ≥зХ≥гБЃйАЪиЈѓгВТйАЪгВЙгБЪгБЂдЄ°иДЗгБЃиКЭзФЯгБЃдЄКгВТж≠©гБНиКЭзФЯгВТиЄПгБњиНТгВЙгБЧгБЯгБУгБ®гБІпљҐзЂЛгБ°еЕ•гВКз¶Бж≠Ґпљ£гБЃзЂЛгБ¶жЬ≠гВТгБЯгБ¶гБЯгБУгБ®гБІгБЩгАВгГЮгГКгГЉгБ®гБѓгАБењГйЕНгВКпЉИдЇЇгБЃењГгБМгВПгБЛгВЛењГгВТй§КгБЖгБУгБ®пЉЙгВТгБЧгБ¶зЫЄжЙЛгБЃдЄНпЉИдЄНеє≥пљ•дЄНжЇАпљ•дЄНеЃЙ)гВТзЫЄжЙЛгВИгВКеЕИгБЂеѓЯзЯ•гБЧгБ¶иІ£жґИгБЩгВЛгБУгБ®гБІгБЩгАВгВµгГЉгГУгВєж•≠гБЃеОЯзВєгБѓпљҐдЄНпљ£гБЃиІ£жґИгБІгБЩгАВ
зЫЄжЙЛгВТгВИгВКзРЖиІ£гБЧгБЃењГгБЃе£БгВТйЩНгВНгБХгБЫгВЛгБЂгБѓвС†и¶Ци¶ЪзЪДи¶Бзі†пЉЪжЄЕжљФгБ™иЇЂгБ™гВКгАБжШОгВЛгБДи°®жГЕгВТжДПи≠ШгБЧгАБзЫЄжЙЛгВТи¶ЛгВЛ(зЫЃгБЂеЕ•гВЛпЉЙвЖТи¶≥гВЛвЖТи®ЇгВЛвЖТзЬЛгВЛпЉИжЙЛгВТдљњгБ£гБ¶зЬЛгВЛпЉЙгБЄгБ®и¶≥еѓЯгБЧгАБжО•гБЩгВЛгБУгБ®гАВвС°иБіи¶ЪзЪДи¶Бзі†пЉЪзЫЄжЙЛгБЃе£∞гБЃгГИгГЉгГ≥гАБе§ІгБНгБХгБЛгВЙдљХгВТдЉЭгБИгБЯгБДгБЛгВТиБЮгБПпЉИеЛЭжЙЛгБЂиА≥гБЂеЕ•гВЛпЉЙвЖТиБігБП(иЗ™еИЖгБЛгВЙиА≥гВТеВЊгБСгВЛ)гБУгБ®гБІзЫЄжЙЛгБЃи®АиСЙгБЃзЬЯжДПгВТи™≠гБњеПЦгВЛгАВвАїеП§дї£гВЃгГ™гВЈгГ£гБЃеУ≤е≠¶иАЕгВљгВѓгГ©гГЖгВєгБѓпљҐеП£гБѓдЄАгБ§иА≥гБѓдЇМгБ§гБВгВЛгБЃгБѓи©±гБЩгБЃдЇМеАНиБЮгБПгБЯгВБгБЂгБВгВЛгАНиЗ™еИЖгБМи©±гБЩгБУгБ®гВИгВКзЫЄжЙЛгБЃи©±гВТиБЮгБПгБУгБ®гБЃжЦєгБМе§ІеИЗгБІгБВгВЛгБ®и®АгБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВгВИгБПиБігБПгБ®пљҐж∞ЧдїШгБНпљ£гБМзФЯгБЊгВМгАМи°МеЛХпљ£гВДи®АиСЙпљ£гБМгБІгВЛгАВж∞ЧдїШгБДгБЯгБУгБ®гВТи°МеЛХгБЩгВЛжДЯжАІпљ£гБМйЂШгБЊгВЛгБ®и®АгБЖгБУгБ®гБІгБЩгАВжДЯжАІ(зЫіжДЯеКЫ)гВТйЂШгВБгВЛгБ®гВїгГ≥гВєгБМйЂШгБЊгВЛгАВеРМгБШзЙ©жµБж•≠гВТгБЩгВЛгБ™гВЙгВїгГ≥гВєгВТйЂШгВБгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ


з†ФдњЃдЉЪпЉТгААгГРгГГгВѓдЇЛжХЕгБѓгБ™гБПгБЫгБЊгБЩпљЮгГРгГГгВѓгБЃи¶ЛгБИгВЛеМЦ
гГРгГГгВѓдЇЛжХЕеѓЊз≠ЦгБЂгБѓз™УгВТйЦЛгБС祯и™НгАБйЩНгВКгБ¶гГСгВ§гГ≠гГ≥гВТзљЃгБПз≠ЙгГЂгГЉгГЂгВТеЃЪгВБгВЛгБУгБ®гВВгБВгВКгБЊгБЩгБМгАБйЫ®гБЃжЧ•гБѓз™УгВТйЦЛгБСеЊМжֺ祯и™НгВДгГИгГ©гГГгВѓгБЛгВЙйЩНгВКгБ¶гГСгВ§гГ≠гГ≥гВТжЬђељУгБЂгБКгБСгВЛпЉЯз≠ЙеЊєеЇХгБЂзЦСеХПгБМгБКгБНгБЊгБЩгАВ
гГРгГГгВѓдЇЛжХЕгВТгБ™гБПгБЩгБЂгБѓж•µеКЫгГРгГГгВѓгБЧгБ™гБДгАБгГРгГГгВѓгБЩгВЛиЈЭйЫҐгВТжЬАе∞ПйЩРгБЂгБ®гБ©гВБгВЛгБУгБ®гБІгБЩгБМгАБдїКеЫЮгБЃз†ФдњЃдЉЪгБІгБѓгГРгГГгВѓжЩВгБЂ3зІТдї•дЄКеБЬж≠ҐгАБгГРгГГгВѓгБЃжУНдљЬжЩВйЦУгАБжУНдљЬй†їеЇ¶гВТи®ШйМ≤гБЩгВЛж©ЯжҐ∞гВТдљњгБ£гБ¶жМЗе∞ОгБЩгВЛеЖЕеЃєгБІгБЧгБЯгАВ
гГИгГ©гГГгВѓгБМгГРгГГгВѓгБЩгВЛиЈЭйЫҐгБѓ1еП∞еИЖпЉИпЉЧпљНпЉЙгВТйЩРеЇ¶гБЂгБЩгВЛгАБеЊМжֺ祯и™НжЩВйЦУ3зІТгГЂгГЉгГЂгАБгГРгГГгВѓгБЃйАЯеЇ¶гБМжЩВйАЯ4пљЛпљНгВТиґЕгБИгВЛгБ®еС®гВКгБЃдЇЇгБМеН±йЩЇгВТжДЯгБШгВЛгБЃгБІжЬАе§ІйАЯеЇ¶гВТж±ЇгВБгВЛдЇЛгВВгГЭгВ§гГ≥гГИгБІгБЧгБЯгАВ
дЉБж•≠и¶ЦеѓЯпЉСгААеЈ•е†ізФ®еЙѓи≥ЗжЭРгБЃеНЄе£≤ж•≠пЉИз•ЮжИЄзЙ©жµБгВїгГ≥гВњгГЉпЉЙ
гБУгБ°гВЙгБЃдЉЪз§ЊгБѓе∞ПгБХгБ™еЈ•еЕЈгБЛгВЙе§ІгБНгБ™еЈ•еЕЈгВТ22дЄЗгВҐгВ§гГЖгГ†еЬ®еЇЂгАБзЈПеЛҐ150еРНгБІдїХеИЖгБСгБЧеН≥жЧ•йЕНйАБгВТи°МгБ£гБ¶гБДгВЛгВїгГ≥гВњгГЉгБІгБЩгАВ
дїКеєіеЕ•з§ЊгБЧгБЯгБ∞гБЛгВКгБЃз§ЊеУ°гБХгВУгБМзЙ©жµБгВїгГ≥гВњгГЉеЖЕгВТйЪЕгАЕгБЊгБІи™ђжШОгБЧгБ¶й†ВгБНгБЊгБЧгБЯгАВгБУгБ°гВЙгБЃз§ЊеУ°гБХгВУгБѓжЦ∞дЇЇгБХгВУгБЂжЧ©гБПгБЛгВЙгВїгГ≥гВњгГЉж°ИеЖЕгВТгБХгБЫгБ¶иЗ™з§ЊгБЃиАГгБИжЦєпЉИзРЖењµпЉЙгАБж•≠еЛЩзЙєжАІгАБеЉЈгБњгВТзРЖиІ£гБХгБЫгАБи¶ЦеѓЯгБЂжЭ•гВЛдЇЇгВТжДЯеЛХгБХгБЫгБ¶гБДгБЊгБЧгБЯгАВ
иЗ™з§ЊгБЃгГОгВ¶гГПгВ¶гВТжГЬгБЧгБњгБ™гБПгВ™гГЉгГЧгГ≥гБЂгБЧгБ¶з§ЊеУ°гБЂи¶Ле≠¶иАЕгБМжЭ•гВЛгБїгБ©гБЂдїХдЇЛгБЂи™ЗгВКгВТжМБгБЯгБЫгАБжЦ∞гБЯгБ™гБУгБ®гБЂеЄЄгБЂжМСжИ¶гБЧгБ¶гБДгБЊгБЧгБЯгАВ
гБВгБЊгВКгБЂгВВзґЇйЇЧгБ™гВїгГ≥гВњгГЉгБ†гБ£гБЯзВЇгАБеЊМжЧ•зЪЖгБІиЗ™з§ЊгВїгГ≥гВњгГЉгБЃйЪОжЃµеїКдЄЛгВТе§ІжЄЕжОГгБЧгБЊгБЧгБЯгАВ
еЕИжЬИе§ІйШ™гГїз•ЮжИЄгБЄз†ФдњЃдЉЪеПКгБ≥зЙ©жµБдЉБж•≠и¶ЦеѓЯгБЂи°МгБ£гБ¶гБЊгБДгВКгБЊгБЧгБЯгАВ
з†ФдњЃдЉЪеЖЕеЃє
пЉСпЉОе•≥жАІгБЃжіїзФ®гВТиАГгБИгВЛ еє≥жИР25еєіи≥ГйЗСжІЛйА†еЯЇжЬђзµ±и®Ии™њжЯїгБЂгВИгВЛгБ®йБЛ迥еЕНи®±дњЭжЬЙе•≥жАІ(е§ІпЉПдЄ≠пЉПжЩЃпЉЙгБѓзіД3500дЄЗдЇЇгАВе•≥жАІгГИгГ©гГГгВѓпЊДпЊЮпЊЧпљ≤пЊКпЊЮпљ∞пЉИеРМпЉЙгБѓзіД23700дЇЇгБ®гАБеЕ®дљУгБЃ0.1пЉЕгБЂгБ®гБ©гБЊгБ£гБ¶гБДгВЛпЉИзФЈжАІ1.9пЉЕпЉЙгАВ пЊДпЊЮпЊЧпљ≤пЊКпЊЮпљ∞дЄНиґ≥гБЃгГИгГ©гГГгВѓж•≠зХМгБѓе•≥жАІпЊДпЊЮпЊЧпљ≤пЊКпЊЮпљ∞гВТеҐЧгВДгБЩгБєгБПгАМгГИгГ©гВђгГЉгГЂгАНгБЃжДЫзІ∞гБІPRгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ е§ІжЙЛеЃЕйЕНдЉЪз§ЊгБѓе•≥жАІеЊУж•≠еУ°жѓФзОЗгВТйЂШгВБгБ¶гБНгБ¶гБКгВКгАБдїКеЊМе•≥жАІгБЃеГНгБНгВДгБЩгБДеКіеГНзТ∞еҐГжХіеВЩгБМењЕи¶БгБ†гБ®жДЯгБШгБЊгБЧгБЯгАВ гБЊгБЯгАБе•≥жАІгБѓеЗЇзФ£гГїиВ≤еЕРгБІдїХдЇЛзФЯжіїгБЃгГРгГ©гГ≥гВєгБМе§ЙеМЦгБЧгАБгГХгГЂгБЂеГНгБНзґЪгБСгВЛгБУгБ®гБМйЫ£гБЧгБПзПЊеЬ®гБЃдЉЪз§ЊгБЃе∞±ж•≠嚥жЕЛ гБІгБѓгВ≠гГ£гГ™гВҐгГЧгГ©гГ≥гБМеЗЇзФ£гБЂгВИгВКгГ™гВїгГГгГИгБХгВМгАБжШЗйА≤гБМйЫ£гБЧгБДгАВ гБЭгБУгБІгАБ
вС†иВ≤еЕРдЄ≠гБЃе•≥жАІгБМеГНгБСгВЛзЯ≠жЩВйЦУгВЈгГХгГИ
вС°еЖНйЫЗзФ®гБЄгБЃгГБгГ£гГђгГ≥гВЄ
вСҐељєиБЈжШЗж†ЉгВИгВКгВВеГНгБНзґЪгБСгВЙгВМгВЛзТ∞еҐГпЉИ ељєиБЈгВИгВКгВВељєеЙ≤гВТдљЬгВЛпЉЙ
гБУгБ®гВТгГЭгВ§гГ≥гГИгБЂз§ЊеЖЕгВТи¶ЛзЫігБХгБ™гБСгВМгБ∞гБ®жДЯгБШгБЊгБЧгБЯгАВ
гААињСеєігАБйЪЬеЃ≥иАЕгБЃжЦєгБЃеЛ§еКіжДПжђ≤гБМйЂШгБЊгВКгБ§гБ§гБВгВЛдЄ≠гАБељУз§ЊгВВдЉБж•≠гБ®гБЧгБ¶гБЃз§ЊдЉЪзЪДи≤ђдїїгАБгВ≥гГ≥гГЧгГ©гВ§гВҐгГ≥гВєгБЃи¶≥зВєгБЛгВЙгАБйЪЬеЃ≥иАЕгБЃжЦєгБЃйЫЗзФ®гВТз©Нж•µзЪДгБЂйА≤гВБгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гБУгВМгБЊгБІгАБгГПгГ≠гГЉгГѓгГЉгВѓгВДжФѓжПіе≠¶ж†°гАБжФѓжПіжЦљи®≠гБЛгВЙгБФзієдїЛгВТгБДгБЯгБ†гБНгАБиБЈе†іи¶Ле≠¶дЉЪгВДгАБдљУй®УеЃЯзњТгБ™гБ©гВТйАЪгБЧгБ¶йЪЬеЃ≥иАЕгБЃжЦєгБЃйЫЗзФ®гБЂеПЦгВКзµДгВУгБІгБНгБЊгБЧгБЯгАВ
гААгБХгВЙгБЂгАБгВИгВКдЄА屧гБЃйЫЗзФ®дњГйА≤гБЃгБЯгВБгАБпЉСпЉРжЬИпЉСпЉРжЧ•гБЂжЭ±дЇђйЪЬеЃ≥иАЕиБЈж•≠иГљеКЫйЦЛзЩЇж†°пЉИжЭ±дЇђйГље∞Пеє≥еЄВпЉЙгБІйЦЛеВђгБХгВМгБЯгАМгГПгГ≠гГЉгГѓгГЉгВѓзЂЛеЈЭгГїйЭТжҐЕгГїдЄЙйЈєеРИеРМйЪЬеЃ≥иАЕйЭҐжО•дЉЪгАНгБЂпЉСпЉУз§ЊгБЃдЉБж•≠гБЃгБЖгБ°гБЃпЉСз§ЊгБ®гБЧгБ¶гГЦгГЉгВєгВТи®≠гБСгБ¶гБДгБЯгБ†гБНгАБйЪЬеЃ≥иАЕгБЃжЦєгБ®гБЃйЭҐжО•гВТи°МгБДгБЊгБЧгБЯгАВеПВеК†гБХгВМгБЯдЉБж•≠гБѓгБ©гБУгВВжЬЙеРНдЉБж•≠гБ∞гБЛгВКгБІгАБеИЭгВБгБ¶еПВеК†гБЃељУз§ЊгБЂењЬеЛЯгБЧгБ¶гБДгБЯгБ†гБСгВЛгБЛдЄНеЃЙгБІгБЧгБЯгБМгАБйЦЛеІЛгБЃеРИеЫ≥гБ®гБ®гВВгБЂе§ІеЛҐгБЃе∞±иБЈеЄМжЬЫгБЃжЦєгАЕгБЂгБКиґКгБЧгБДгБЯгБ†гБНгАБгБВгВЙгБЯгВБгБ¶йЪЬеЃ≥иАЕгБЃжЦєгАЕгБЃеЛ§еКіжДПжђ≤гБЃйЂШгБХгБЂжХђжЬНгБДгБЯгБЧгБЊгБЧгБЯгАВгБФењЬеЛЯгБДгБЯгБ†гБНгБЊгБЧгБЯзЪЖжІШгАБгБВгВКгБМгБ®гБЖгБФгБЦгБДгБЊгБЧгБЯгАВгБЊгБЯгАБйЭҐжО•гБЃй†ЖзХ™еЊЕгБ°гБІгАБйХЈжЩВйЦУгБКеЊЕгБЯгБЫгБЧгБЯгБУгБ®гАБжЈ±гБПгБКи©ЂгБ≥зФ≥гБЧдЄКгБТгБЊгБЩгАВ
гААжЬАеЊМгБЂгБ™гВКгБЊгБЧгБЯгБМгАБгБКдЄЦи©±гВТгБЧгБ¶гБПгБ†гБХгБ£гБЯгГПгГ≠гГЉгГѓгГЉгВѓгБЃзЪЖжІШгБЂгБКз§ЉзФ≥гБЧдЄКгБТгБЊгБЩгАВгБВгВКгБМгБ®гБЖгБФгБЦгБДгБЊгБЧгБЯгАВ

дїКеєігВВгГОгГЉгГЩгГЂи≥ЮгБЃи©±й°МгБМжЦ∞иБЮзіЩйЭҐгВТгБЂгБОгВПгБЩе≠£зѓАгБЂгБ™гВКгБЊгБЧгБЯгАВ
дїКеЫЮжЧ•жЬђдЇЇгБЃеПЧи≥ЮгБ®гБДгБЖжШОгВЛгБДи©±й°МгВВгБВгВКгБЊгБЧгБЯгБМгАБеє≥еТМи≥ЮгБЂйБЄгБ∞гВМгБЯгГСгВ≠гВєгВњгГ≥гБЃ
гГЮгГ©гГ©гГїгГ¶гВєгГХгВґгВ§гБХгВУгБЃеПЧи≥ЮгБЂжДЯеЛХгБЧгБЊгБЧгБЯгАВ
17ж≠≥гБЃе∞Се•≥гБМдЇЇгАЕгБЂдЄОгБИгБЯеЛЗж∞ЧгАМдЄАдЇЇгБЃе≠РгБ©гВВгАБдЄАдЇЇгБЃеЕИзФЯгАБдЄАеЖКгБЃжЬђгАБдЄАжЬђгБЃгГЪ
гГ≥гБМдЄЦзХМгВТе§ЙгБИгВЙгВМгВЛгАНгБ®жШ®еєігБЃи™ХзФЯжЧ•гБЂеЫљйА£гБІжЉФи™ђгБХгВМгБЯгБ®гБЃдЇЛгАВйКГеЉЊгБЂеАТгВМгБ¶гВВ
и®ігБИзґЪгБСгВЛеЛЗж∞ЧгБВгВЛе∞Се•≥гБЃењЧгБЂењГгВТжЙУгБЯгВМгБЊгБЧгБЯгАВ
гБХгБ¶гАБзІЛгБЃдЇ§йАЪеЃЙеЕ®йА±йЦУгВВзД°дЇЛгБЂзµВгВПгВКгБЊгБЧгБЯгБМгБУгВМгБЛгВЙеєіжЬЂгБЂеРСгБСгБ¶гВИгВКгАМеЃЙеЕ®гГї
еЃЙењГгБЃзґЩзґЪгБУгБЭгБМеСљзґ±гАН
йЗНе§ІдЇЛжХЕгВЉгГ≠гАБињљз™БдЇЛжХЕгВЉгГ≠гАБжІЛеЖЕгГїйІРиїКе†іеЖЕдЇЛжХЕгВЉгГ≠гВТзЫЃжМЗгБЧгБ¶еЃЙеЕ®иђЫзњТдЉЪгВТи°МгБД
гБЊгБЩгАВ
11/25.26гАА18пЉЪ00пљЮгААеЇІйЦУгВїгГ≥гВњгГЉ
11/27.28гАБ12/4гАА18пЉЪ45пљЮгААеЕЂзОЛе≠РгВїгГ≥гВњгГЉ
11/30гАБ12/7гАА9пЉЪ00пљЮгААе∞Пеє≥еЦґж•≠жЙА
12/1гААгААгАА11пЉЪ00пљЮгАА гААдЄЙиК≥еЦґж•≠жЙА
12/5гАА13,15,гАА16пЉЪ00пљЮгААеЕЂжљЃеЦґж•≠жЙА
дЇ§йАЪдЇЛжХЕгБЃйШ≤ж≠ҐгБЂеРСгБС
гÿ祯еЃЪи¶Бзі†пЉЪеН±йЩЇгГЮгГГгГЧеПКгБ≥зіНеУБеЕИеС®иЊЇгБЃзКґж≥БеЫ≥гБІеН±йЩЇзЃЗжЙАгВТжККжП°
гГїдЄН祯еЃЪи¶Бзі†пЉЪе≠£зѓАгАБ姩еАЩгАБжЩВйЦУгАБйБУиЈѓзКґж≥БгБЃе§ЙеМЦгБЄгБЃеѓЊењЬпЉИKYTгВЈгГЉгГИгБЂгВИгВЛеН±йЩЇдЇИжЄђ
жДПи≠ШUPпЉЙ
гГїдЄНеЃЙеЕ®и°МеЛХпЉЪеИЭдїїиАЕи®ЇжЦ≠гБІгБЃиЗ™иЇЂгБЃйБЛ迥и°МеЛХгБЃзҐЇи™НеПКгБ≥пЊДпЊЮпЊЧпљ≤пЊМпЊЮпЊЪпљЇпљ∞пЊАпЊЮпљ∞гБЃзҐЇи™Н
гВТи°МгБДгВ≥гГДгВ≥гГДеЃЙеЕ®гБ™иБЈе†ідљЬгВКгВТгБЧгБ¶гБДгБНгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ
жЬ®гБЃиСЙгБЃиЙ≤гВВе∞СгБЧе§ЙгВПгВКеІЛгВБгБ¶зІЛгВТжДЯгБШгБЊгБЩгАВзІЛгБѓгВ§гГЩгГ≥гГИгВВе§ЪгБДгБІгБЩгАВ
гГїзІЛгБЃдЇ§йАЪеЃЙеЕ®йА±йЦУпЉИ9/21пљЮ30пЉЙ
гГїе§ЪжС©жФѓйГ®дЇЛжХЕйШ≤ж≠Ґе§ІдЉЪпЉИ9/22пЉЙ
гГїгГИгГ©гГГгВѓгБЃжЧ•пЉИ10/9пЉЙз≠Й
дЄАжЧ•дЄАжЧ•еЃЙеЕ®йБЛ迥гВТењГгБМгБСгБ¶ж∞ЧжМБгВИгБПдїХдЇЛгВТгБЧгБЯгБДгВВгБЃгБІгБЩгБ≠гАВ
гБХгБ¶гАБ8жЬИдЄЛжЧђгВИгВКеРДгВїгГ≥гВњгГЉгБЂгБКгБДгБ¶гГ™гГЉгГАгГЉдЉЪгБЃгВ≠гГГгВѓгВ™гГХгГЯгГЉгГЖгВ£гГ≥гВ∞гВТйЦЛгБДгБ¶гБКгВКгБЊгБЩгАВ
пЉИдЄ≠ењГгГ°гГ≥гГРгГЉгБѓгГЩгГЖгГ©гГ≥пЊДпЊЮпЊЧпљ≤пЊКпЊЮпљ∞гАБгГИгГђгГЉгГКгГЉпЉЙ
гБУгБЃдЉЪгБЃзЫЃжМЗгБЩгБ®гБУгВНгБѓгАМжШОгВЛгБПгАБеЕГж∞ЧгБІгАБдїХдЇЛгБМж•љгБЧгВБгВЛиБЈе†ігБ•гБПгВКгАНгВТеЕ®з§ЊдЄАдЄЄгБ®гБ™гБ£гБ¶жО®
йА≤гБЧгБ¶гБДгБПгБУгБ®гБІгБЩгАВ
гАМдїХдЇЛгВТж•љгБЧгВАгАНгБ®и®АгБЖгБ®иґ£еС≥гВДйБКгБ≥гБЃеїґйХЈгБЂеПЦгВЙгВМгВЛдЇЇгВВгБДгВЛгБЛгВВгБЧгВМгБЊгБЫгВУгБМгАБгБУгБУгБІгБДгБЖ
ж•љгБЧгВАгБ®гБѓгАБ
гГїеЃЙењГгБЧгБ¶дїХдЇЛгБМеЗЇжЭ•гВЛзТ∞еҐГдљЬгВКгБЄгБЃеПВзФї
гГїгГ†гГАгАБгГ†гГ™гАБгГ†гГ©гВТгБ™гБПгБЧгБ¶еЃЙеŮ祯еЃЯгБ™дїХдЇЛгВТгБЩгВЛ
гГїжШО祯гБЂгАМдЇЇгБЃгБКељєгБЂзЂЛгБ£гБ¶гБДгВЛдїХдЇЛгАНгБ†гБ®и™Ни≠ШгБЧгАБжЫігБ™гВЛзЙ©жµБжКАи°УеРСдЄКгВТеЫ≥гВЛ
гГїиЙѓгБНдї≤йЦУгАБеК©гБСеРИгБДгБЃжАЭгБДгВДгВКгБЃгБВгВЛдЇЇйЦУйЦҐдњВгВТзѓЙгБП
дЇЛгБІгБЩгАВ
гБЭгБЃзВЇгБЂ
гГїжѓОжЬИзµМеЦґиАЕгАБзЃ°зРЖиАЕгАБгГ™гГЉгГАгГЉгБ®гБЃжіїзЩЇгБ™жДПи¶ЛдЇ§жПЫгБЃе†ігВТдљЬгВКгБЊгБЩгАВ
гГїз§ЊдЉЪдЇЇгБ®гБЧгБ¶гБЃжХЩй§КгВТйЂШгВБгВЛе†ігВТдљЬгВКгБЊгБЩгАВ
гГїзЙ©жµБжКАи°УгВТйЂШгВБгВЛгБЯгВБгБЃе†ігВТдљЬгВКгБЊгБЩгАВ
зЃ°зРЖиАЕдЉЪгАБгГ™гГЉгГАгГЉдЉЪгБЃжіїеЛХгБЃдЄ≠гБІеЗЇгБЯи™≤й°МгБЂгБ§гБДгБ¶гБѓPOCAгВµгВ§гВѓгГЂгВТеЫЮгБЧжФєеЦДгБЃеПЦгВКзµДгБњгВТи°М
гБ£гБ¶гБДгБНгБЊгБЩгАВ
й≠ЕеКЫгБВгВЛгГИгГ©гГГгВѓйБЛйАБж•≠гВТзЫЃжМЗгБЧгБ¶гАБе∞СгБЧгБЪгБ§гБІгВВгВ≥гГДгВ≥гГДйА≤гВБгБ¶и°МгБНгБЊгБЩгАВ
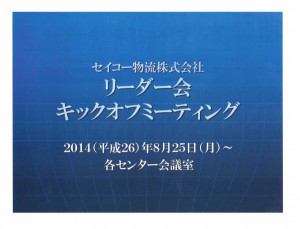
е§ПгВВгБЭгВНгБЭгВНзµВгВПгВКжЬЭжЩ©жґЉгБЧгБПгБ™гБ£гБ¶гБНгБЊгБЧгБЯгАВ
гБУгБЃеЇ¶гГЫгГЉгГ†гГЪгГЉгВЄгВТгГ™гГЛгГ•гВҐгГЂгБДгБЯгБЧгБЊгБЧгБЯгАВзЬЯе§ПгБЃжЪСгБХгБЂгВВгБЛгБЛгВПгВЙгБЪ
гБДгБ£гБ±гБДгБЃзђСй°ФгБІжТЃељ±гБЂеНФеКЫй†ВгБНгБВгВКгБМгБ®гБЖгБФгБЦгБДгБЊгБЩгАВ
гБХгБ¶гАБгГЦгГ≠гВ∞йЦЛеІЛгБЂељУгВКдљХгВТжЫЄгБУгБЖгБ®гБЛжАЭгБ£гБ¶гБДгБЯгБ®гБУгВНжЬђз§ЊеАЙеЇЂжФєдњЃеЈ•дЇЛ
гБЃзВЇиНЈзЙ©гВТжРђеЗЇдЄ≠гБЂеП§гБДдЉЪз§ЊгБЃзЬЛжЭњгВТзЩЇи¶ЛгБЧгБЊгБЧгБЯгАВ
гБКгБЭгВЙгБПпЉФпЉШеєідљНеЙНгБЃгВВгБЃгБ†гБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ
гБЭгБУгБІдїКеЫЮгБѓдЉЪз§ЊеИЭењГгАБзµМеЦґзРЖењµгБЂгБ§гБДгБ¶жЫЄгБЛгБНгБЊгБЩгАВ
ељУз§ЊгБЃзµМеЦґзРЖ圵жДЯиђЭгБ®е•ЙдїХпљ£гБѓеЙµж•≠иАЕгБЃжЇЭеЖЕзЊ©еєЄдЉЪйХЈгБМдЉЪз§Њи®≠зЂЛжЩВгБЂ
ж±ЇгВБгБЯи™УгБДгБІгБЩгАВ
гБКеЫљпЉИйБУиЈѓпљ•и°МжФњпЉЙгАБгБКеЃҐжІШгАБгБКеПЦеЉХеЕИжІШгБМгБВгВЛгБЛгВЙгБУгБЭгВПгБМз§ЊгБМжіїгБЛгБХгВМгБ¶
гБДгВЛгБУгБ®гБЂжДЯиђЭгБЧгАБжЧ•гАЕгБЊгБШгВБгБЂжКАи°УгВТз£®гБНгАБеЃЙеŮ祯еЃЯпљ•дЄБеѓІгБІеКєзОЗгБЃиЙѓгБД
иЉЄйАБгВµгГЉгГУгВєгБІгБФе•ЙдїХгБХгБЫгБ¶й†ВгБПжАЭгБДгБМгБУгВБгВЙгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
зІБгБѓзРЖењµгБѓжЩВгБМе§ЙгВПгБ£гБ¶гВВж±ЇгБЧгБ¶е§ЙгВПгВЙгБ™гБДгВВгБЃгБ†гБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ
еЙµж•≠й≠ВгВТжЧ•гАЕеЃЯиЈµгБЧжђ°гБЃжЩВдї£гБЂгБНгБ°гВУгБ®гБ§гБ™гБОгБЯгБДгБ®жАЭгБДгБЊгБЩгАВ